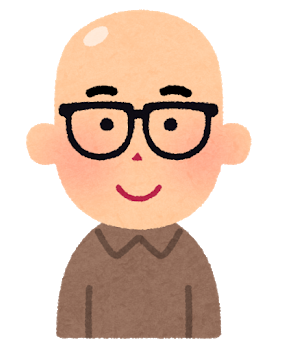
今回は無形資産についての学習です。有形固定資産に比べると重要度は落ちますが気を抜かないでいきましょう。記事内容は個人的なメモに過ぎませんのであくまでも参考としてご覧ください。この記事を参考されたことによる結果について、いかなる責任も負いかねますので何卒よろしくお願いいたします。
目次
無形資産 ★★★
無形資産の定義
無形資産とは物理的な実態を持たない金融資産以外の資産を言う
主な無形資産の種類
マーケティング関連
Trademarks 商標
Tradenames 商号
会社や商品の存在を表し、また他者と明確に区別するための単語、フレーズあるいはシンボルを使用する法的な権利である。米国特許商標庁に登録した商標や商号は10年毎の更新は無制限に認められる。従って、これらは耐用年数無制限である。
顧客関連
Customer lists 顧客リスト
芸術関連
Copyrights 著作権
契約関連
Franchises フランチャイズ
Licensing agreements ラインセンス契約
技術関連
Patente 特許権
特定の発明等に対して米国特許商標庁より与えられる権利である。有効期限は20年間であり、償却は20年以内で行わなければならない。
測定
無形資産は取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で測定する。
仕訳
D) Patents xxx C) Cash xxx
D) Amortization xxx C) Accumulated amortization-Patent xxx
法的、規制上、あるいは契約上、その他の要素を勘案しても耐用年数の上限を設けるような要因が見当たらない場合、償却は行わないが減損の対象となる。
耐用年数が無期限の無形資産の減損
耐用年数が無期限の無形資産については、時の経過に応じて価値が減少しないため償却は行わないが、その代わり減損の対象になる。
手順
減損の発生可能性を判断する定性的評価を行う。財務パフォーマンスの低下など。
この結果、公正価値と簿価を実際に比較する定量的評価が必要とされた場合のみ、公正価値の測定が必要となる。
販売・リース目的のソフトウェア
この論点はソフトウェアのコストにかかる3つの開発フェイズにおいて、それぞれどのように会計処理をするのかが大切。
Stage 1 技術的可能性の確立前
会計処理:研究開発費として即時費用化
例:詳細なプログラムの設計の完成に要した費用、技術的可能性確立のために発生したプログラムコーディングコスト、テストコスト
この段階ではまだ新しい技術が実用化されるか不明なため、保守主義の観点から即時費用化を行う。
Stage 2 技術的可能性の確立後、販売可能性を確立するまで
会計処理:ソフトウェアとして無形資産計上後、経年で償却
例:技術可能性確立後のコーディングコスト、テストコスト(確立後というのがポイント)、製品マスターの作製費用
この段階では技術として確立しているので資産としてみなされる。
Stage 3 販売可能性を確立後
会計処理:棚卸資産として計上され、販売時に売上原価となる
例:トレーニング機材へのマスター複製費用、梱包費用
販売・リース目的のソフトウェアの償却方法
上記、Stage 2で資産計上された償却の方法。
以下の2つの方法の計算結果のうち大きい方を必要として計上
(1)ソフトウェアコスト ÷ 耐用年数 ⇨定額法
(2)ソフトウェアコスト × 当期の収益 ÷ 見積総収益
更に償却後の簿価をNet Realizable Value = Selling – Selling costsと比べて簿価の方が高ければNRVまで簿価を引き下げなければならない。
例)A社はx1年12月31日ソフトウェアコスト$10,000を資産計上した。耐用年数は5年である。見積総収益は$1,000,000、今期の収益は$400,000であった。またNet Realizable Valueは$5,000であった。
(1)$10,000 ÷ 5年 = $2,000
(2)$10,000 x $400,000 ÷ $1,000,000 = $4,000
これに償却額は$4,000となり簿価は$10,000 – $4,000 = $6,000である。
この簿価$6,000とNRV$5,000を比べると簿価の方が大きいので簿価をNRVまで引き下げる。よって簿価は$5,000となる。
研究開発費
研究開発費の例
研究成果の用途探索、代替製品の試験、製品または製造プロセスの改変、新技術のための治具、金型等、商業生産に転用不可能な試作ライン
⇨要は目新しそうで、転用不可能なものが研究開発費、それ以外は違う
今日はここまでです。
P



コメント